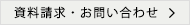カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (3)
- 2025年2月 (5)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (1)
- 2020年1月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (4)
- 2019年7月 (1)
- 2019年5月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (2)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (1)
- 2017年9月 (1)
- 2017年8月 (1)
- 2017年7月 (2)
- 2017年4月 (1)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (2)
- 2016年8月 (1)
- 2016年6月 (1)
- 2016年5月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (4)
- 2015年11月 (1)
- 2015年9月 (5)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (6)
- 2015年5月 (3)
- 2015年3月 (3)
- 2015年1月 (1)
- 2014年12月 (6)
- 2014年11月 (6)
- 2014年10月 (1)
- 2014年8月 (4)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (1)
- 2013年12月 (5)
- 2013年11月 (3)
- 2013年10月 (1)
最近のエントリー

HOME > コラム > 福岡注文住宅・Ua値・C値・福岡市住宅設計・価格上昇で家づくりを断念しない考え方
コラム
福岡市東区工務店&一級建築士事務所・清武建設
< 共用部分重視の家づくり・福岡市建築士相談 | 一覧へ戻る | 福岡市工務店・注文住宅・おすすめの玄関収納・土間収納 >
福岡注文住宅・Ua値・C値・福岡市住宅設計・価格上昇で家づくりを断念しない考え方

https://youtu.be/RNf4nN9-Yew
断熱性向上で大空間の家が実現。
【物価上昇の今の家づくり】
ウッドショック・インフレ時期の家づくりを考える
(家づくりお役立ち資料を請求する)
https://www.kiyotake.co.jp/reserve/

世界各国の中央銀行は
金利を上げている状況です。
しかし所得が横ばいの日本では、
日銀の低金利政策が続いています。
世界の投資家は金利が低い円を売り、
金利が上がるドルを買います。
円が売られるので円安になり、
円安になると、
輸入する原材料が上がります。
当然、建材価格も上がり、
建築費用も上がる傾向です。
さらに世界的に、エネルギーを使わず、
二酸化炭素を削減の動きもあります。
ハイスペックな標準仕様が、
光熱費削減(低炭素)になり、
住宅会社の技術差の印象があります。
しかし、ハイスペック材料の取付のみで
住宅会社の技術差ではありません。
円安による価格上昇の時期に、
ハイスペックな建材を使えば、
高額な住宅価格になります。
ハイスペックな建材が、
Ua値、C値を低くし、
エネルギー消費量を減らしますが
冷暖房が不要な時期は、
Ua値、C値が低くなる効果は、
体感できません。
夏や冬でも、
窓から少し離れると、
体感差はありません。
毎月の住宅ローンが増えても、
体感的に変わらず、
光熱費も削減されなかった場合、
ハイスペックな建材の住宅は、
収支上のメリットが
現在の状況では少ないです。
年収より
住宅ローンの借り入れ可能額を
把握します。
建築資材が上昇し、
宅地価格も上昇しても、
約30年前から平均年収は同じで、
住宅取得の総予算を変えることは
物理的に不可能です。
では、どのようにすれば・・・?
ハイスペックな建材に費用をかける?
屋根材の耐久性に費用をかける?
キッチンに費用をかける?
ウッドショックの木材価格上昇で
国産木材を使う検討も必要です。
費用をかける部分と、
かけない部分のメリハリを
付けるしかありません。
その組み立てを
弊社の建築士スタッフと
一緒に考えませんか?
(家づくりお役立ち資料を請求する)
https://www.kiyotake.co.jp/reserve/

【Ua値】
物件ごとに計算で求められる数値
建物の各部位の熱損失量を合計し、
建物外皮の面積で割ったものが、
外皮平均熱貫流率(Ua値)です。
「家の外へ熱量が逃げる目安」
を表す数値だといえます。
断熱、窓、屋外表面積により変わり、
物件ごとに計算で求めます。
一般的な住宅仕様例で予想される
0.9程度から0.5程度のスペックは、
樹脂窓、トリプルガラス、断熱の変更で
数百万円以上の増額が予想されます。
特に、昨今の資材価格の高騰で
それ以上かもしれません。
夏冬の電気代は増えますが、
年間平均0.3万円、
省エネになったと仮定し、
0.3万円x12か月x40年=144万円
≦ 300万円?(建材増額分)
快適性も大切ですが、
建材追加額が上回る可能性があり、
費用対効果も大切です。
※近年、建材費が流動的で、
さらに上昇する傾向です。
【Q値】 物件ごとに計算で求める数値
Q値(熱損失係数)は、
その家の熱の逃げやすさを表す数値です。
Q値=(各部の熱損失量の合計+換気による熱損失量の合計)÷ 延床面積
で求められ、この数値が小さいほど、
断熱性が高い家となります。
Q値の低い家は、
冬は暖房であたためた熱が、
夏は冷房で冷やした冷気が
外へ逃げにくく、
冷暖房費がかかりにくい、
省エネ性能が高い家といえます。
上記Ua値と同じように、
建材を変更(建材増額)すれば
容易に改善されます。
2013年から、Q値に代わって、
Ua値が省エネルギー基準になりました。
【C値】
現地で気密測定して求められる数値
住宅の気密性能を表す数値がC値。
その家の床面積に対して、
どの程度の隙間面積が存在するか、
表した数値になります。
一般的な注文住宅の仕様例
・隙間の合計70 c㎡ ・床面積100㎡
C値は 70 c㎡ ÷ 100㎡ = 0.7 [c㎡/㎡]
※無垢材の杉材(国産材)筋カイで
構造耐力を考える場合が多いですが、
C値を上げる為には、
外壁面に構造面材を貼ればよいです。
(シックハウス要検討です。)
50万円程度の追加が必要が
30坪の家の場合は予想されます。
(木材高騰に大きく左右されます。)

(家づくりお役立ち資料を請求する)
https://www.kiyotake.co.jp/reserve/
タグ:
(HOME PLAN KIYOTAKE 一級建築士事務所 清武建設) 2022年4月16日 17:45
< 共用部分重視の家づくり・福岡市建築士相談 | 一覧へ戻る | 福岡市工務店・注文住宅・おすすめの玄関収納・土間収納 >






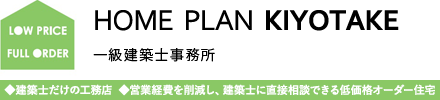
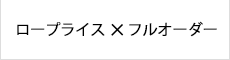
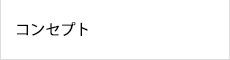
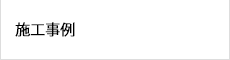
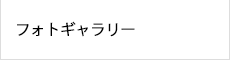
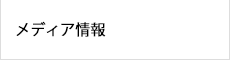
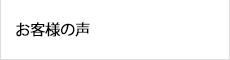
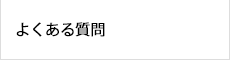
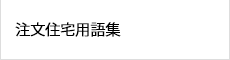
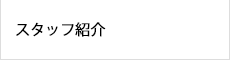
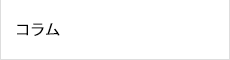
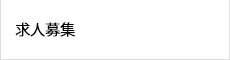
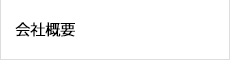


 〒812-0053 福岡市東区箱崎7-2-14 kiyotakeビル
〒812-0053 福岡市東区箱崎7-2-14 kiyotakeビル